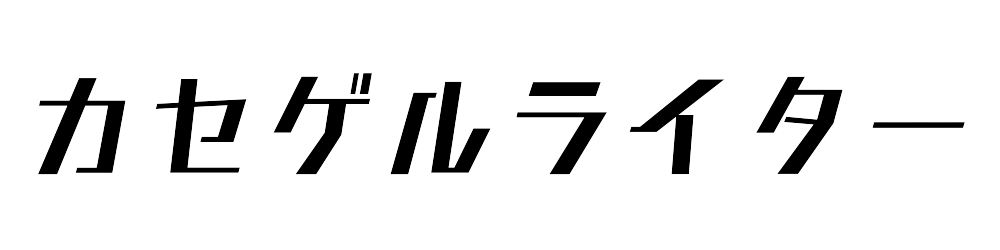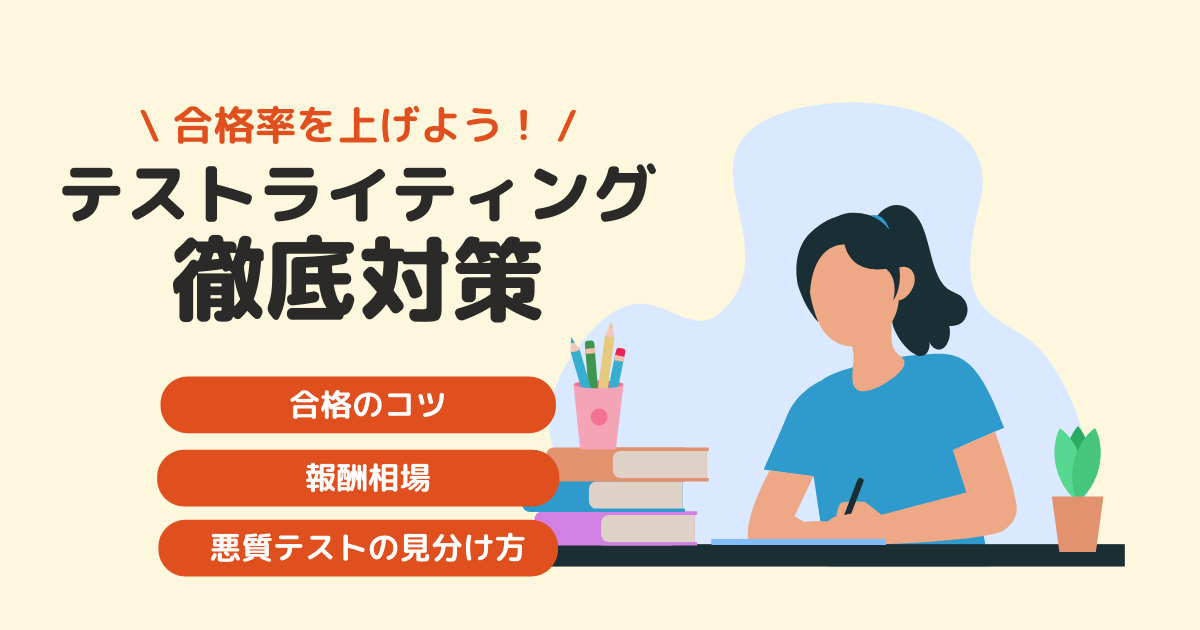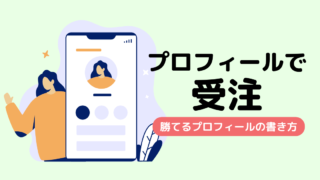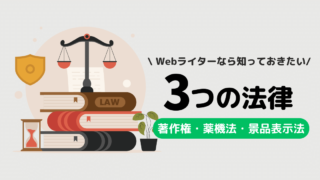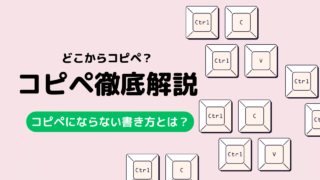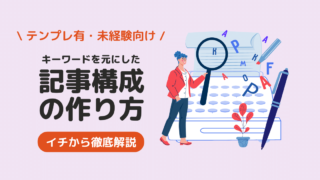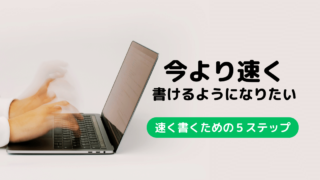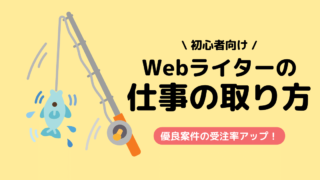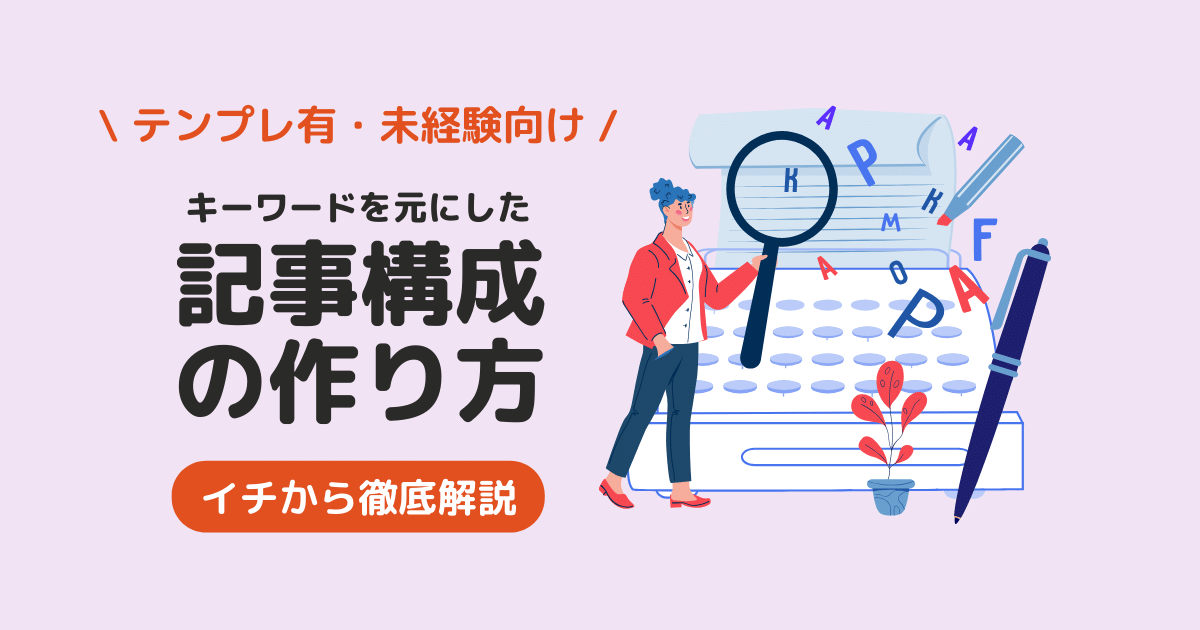「テストライティングって、Webライティングの世界では普通のことなの?」
「テストライティングは報酬が10円って書いてあるけれど、それが当たり前?」
「ぜんぜんテストライティングに合格できない(泣)」
クライアントがWebライターを採用する際、その実力などを「テストライティング」によって判断します。
「Webライターとしてのスキルを測るためにテストがあります」と言われれば、それ自体は納得できるものです。しかし、実際にテストライティングを目の前にすると、冒頭で紹介したようなさまざまな疑問や報酬への不安がでてくるのではないでしょうか。
また「ぜんぜん採用されず、テストライティングばかり書いている」と嘆くWebライター初心者の方は少なくありません。
この記事では、テストライティングとはどのようなテストなのか、そして合格するコツを紹介します。また、テストライティングを使った悪質な案件についても解説していますので、この記事を読んで、テストライティングに関するあらゆる悩みや不安を解消しましょう!
テストライティングとは

テストライティングとは、Webライターのライティングスキルやコミュニケーション能力を判断するための「お試しの記事制作」のことです。クライアントが新しいWebライターへの依頼を考えている際に、事前確認としてよく実施されます。
Webライター「初心者」か「経験者」かに関係なく、新しい契約の前にテストライティングを依頼されることは珍しくはありません。
Webライターのスキルは、プロフィールや応募文だけで判断するのは難しいものです。実績の乏しいWebライターなら、なおさら判断に困ります。Webライター初心者の場合、プロフィールがよく書けていても、スクールの講師が添削したもので、実力ではない可能性もあります。
実績が豊富にあるようなWebライターの場合でも、クライアントが求める人材としてマッチしているかは別の話です。仕事を進める上では、コミュニケーションといった点も重要となるからです。
そこで登場するのがテストライティングです。
案件の正式な依頼前にかんたんな記事を書いてもらい、それを見てクライアントはライティングスキルを判断します。また、このやり取りを通して、仕事の進め方の上でも問題ないかを確認するのです。
Webライターのプロフィールや案件応募時のアピール文がエントリーシートだとすれば、テストライティングは一次面接といったイメージです。
テストライティングはいかに「合格率」を上げるかが重要
通常、案件の応募は「落ちることにめげずに、まずはたくさん応募しよう」と言われます。もちろん採用率を上げることは重要ですが、同じ採用率1%なら、100件の応募と1000件の応募では、沢山応募するほうが多くの案件を獲得できるからです。
しかし、応募の結果、テストライティングに進めた場合は、一件あたりの合格率を上げることに集中しましょう。なぜなら、テストライティングも「納品」して「著作権を譲渡」するからです。
つまり、テストライティングで納品した文章は、不合格だったからといって、別の会社のテストライティングで使ったり、サンプル文書にすることはできないのです。
著作権を譲渡した文章は、たとえ自分の書いた文章でも、勝手にほかの場面で利用してはいけません。
テストライティングは通常の業務と同じ労力がかかることを考えると、不合格のダメージが大きいのもうなずけます。
テストライティングの報酬相場は半額と言われています。つまり、不合格の場合、通常業務と同じ労力で半額しか支払われず、実績にもならないのです(泣)
そのためテストライティングは、数をこなすことよりも、合格率を上げることが重要なのです。
テストライティングの実施パターン
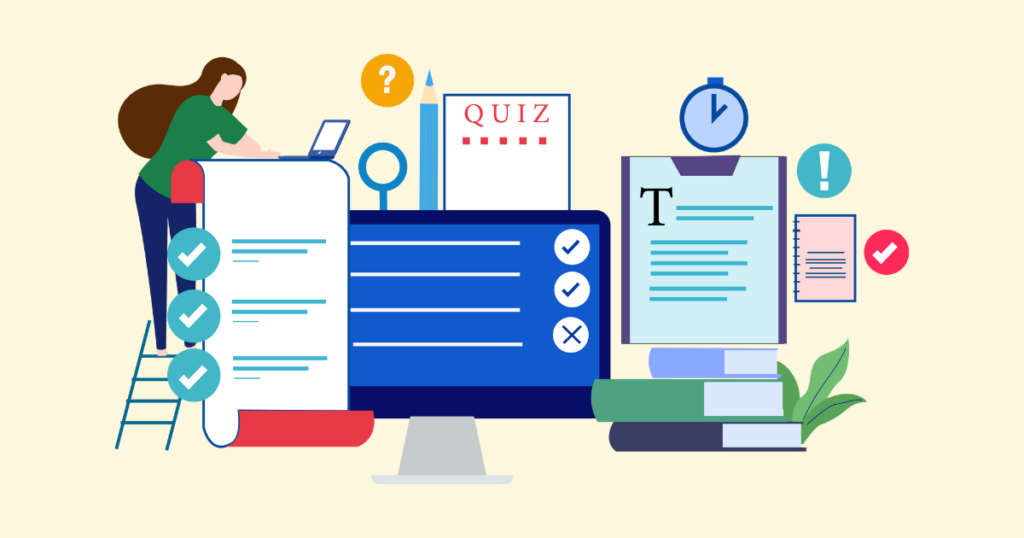
まず、テストライティングの方法を確認しておきましょう。テストライティングは、主に以下の3パターンのいずれかで実施されます。
- 記事の構成作成+執筆
- 執筆のみ
- 専用テスト
それぞれ次のような特徴があります。
記事の構成作成+執筆
記事の構成作成から執筆まで、Webライターとしてのひと通りの仕事を対象としたテストです。
大まかな内容としては、クライアントから掲載を予定しているメディアや対策キーワードをもらい、その内容を元に構成と原稿を作成します。
このテストは、Webライターの経験や実績がある方向けに実施されます。案件としては、文字単価2円以上の案件やSEO対策を含む案件のテストライティングであるケースが主です。
執筆のみ
クライアントから提供される構成に従って、執筆のみを行なうテストです。Webライター初心者の方に向けたテストとして実施されます。基本的なライティング能力の確認が主な目的です。
専用テスト
一部の企業では、ライティング能力を測定するための専用のテストを用意しているケースもあります。
ランサーズやクラウドワークスといった、クラウドソーシングサイトで設けられているWebライティングの検定も、専用テストの一種といえます。
例えば選択式の問題が出題されたり、数百字程度の執筆が求められたりします。多くのライターを選考する際に使われるテスト方法で、通常の案件応募で用いられるのは稀です。
テストライティングでチェックされる内容

テストライティングでは、どのような点をチェックされているのか知っておくことも大切です。主に確認される下記の項目をしっかりと確認しておきましょう。
- オリジナル文章かどうか(コピペ記事ではないこと)
- クライアントの要望に対する理解力
- リサーチ力と文章力
- 納品までの期間・執筆スピード
- ビジネスマナー
オリジナル文章かどうか(コピペ記事ではないこと)
まずはライターの基本、コピペ文章ではない、オリジナルの文章であることが求められます。
納品するテストライティングの文章は、かならずコピペチェックツールを使い、コピペ判定されないことを確認してから納品するようにしましょう。
コピペチェックツールとは、文章がコピペされている可能性を自動で判断するツールです。コピペは人手での判断が難しいため、通常、コピペ記事かどうかの判断はチェックツールを用いて行なわれます。
クライアントからコピペチェックの指定がない場合でも、チェックツールによる確認は必要です。例えば、無料で利用でき、利用者の多いコピペチェックツールは「CopyContentDetector®」などを使って、自身でも納品前にチェックしましょう。
Webライター初心者の場合、コピペしていないのに、コピペだとチェックツールに判定されてしまうことがあります。
これは必ずしもツールの精度の問題ではなく、記事作成の方法が適切でないために意図せずコピペになっていることがあります。こちらの記事を参考にして、コピペと判断されない文章の書き方を身につけましょう。
クライアントの要望に対する理解力
すべての仕事において、クライアントの要望理解は欠かせません。同じWebライティングの仕事でも、トンマナの指定やスピード感が異なるのは当然です。一つひとつのクライアントと真摯に向き合って、要望を理解することが大切です。
リサーチ力と文章力
リサーチ力と文章力はWebライターとしての本髄のスキルです。どれほど内容を理解し、ユーザーの要望に合わせて、わかりやすく記事を書くかが勝負となります。
納品までの期間・執筆スピード
テストライティングはあくまでもテストであるため、その後の通常時の契約内容を想定してやりとりが行なわれることもあります。例えば、月に何本執筆可能か、発注から納品までは何日必要か、といった話です。
ここで重要なのは、クライアントの求めるレベルをクリアすればOKということです。早ければ早いほうがよい、多ければ多い方がよい、というわけではありません。将来的に自分の首を絞めかねないので、無理なアピールは止めましょう。
納品日より前に記事を作成し終わったからといって、クライアントに特別求められていなければ、早く納品する必要はありません。時間があるなら文章を再度一読し、改善点がないか確認してみましょう。その上で、余裕を持って納品対応することをおすすめします。
もちろん、ライターとして稼いでいくためには執筆スピードも重要です!しかし、それでもまずは品質優先!品質を確保できるようになったらスピードアップに取り組みましょう。
ビジネスマナー
いくらクラウドソーシングサイトを通して知り合った仲でも、お互い人間です。気持ちよく仕事を進めるためにはビジネスマナーが重要となります。
Webの世界でも基本的なビジネスマナーは一般と同じです。チャットの文章にも人柄は表れます。丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
合格率を上げるためのポイント7選

テストライティングでチェックされるポイントへの対策は、いわば最低限の対策です。合格率を上げて、より高い評価やその後の安定した仕事を得るために、押さえておきたい7つのポイントを紹介します。
- クラウドソーシングサイトの検定を受験する
- トンマナを守る
- 掲載予定のメディアを確認する
- 簡潔かつ丁寧なコミュニケーションを心がける
- 指示内容をしっかりと確認する
- 一晩寝かせて確認し、余裕を持って納品する
- 文字数は気持ち多めにする
クラウドソーシングサイトの検定を受験する
まず、テストライティングで何度か不合格になってしまった方は、基本的なWebライティングスキルが不足している可能性があります。そのため、スキル不足かどうかを判断するために、専用テストであるWebライティング検定を受験してみましょう。
クラウドワークスなら「Webライター検定」、ランサーズなら「Webライティング技能検定試験」という名前で、検定を受けられます。
自分のスキルを客観的に示す「資格」の影響は大きいものです。無料で何度も受験できるので、まだ受けたことの無い方は、勉強も兼ねて検定を受けるのをおすすめします!
検定の合格はプロフィールの強化にもつながるため、一石二鳥です!
また、「基本的なWebライティングスキルはあるものの、競争力を高めたい」という方には、SEOの勉強がおすすめです。SEO対策を学ぶことは、Webライティング能力を上げることにもつながります。
トンマナを守る
トンマナはしっかりと確認し、かならず守りましょう。
トンマナを守るコツは、ですます調といった文章方針は執筆前に確認し、漢字とひらがなの書き分けといった細かいルールは執筆後にまとめてチェックすることです。
トンマナの数が多いと、トンマナを気にしながら執筆して効率が悪くなったり、見落としが増えてしまったりしがちです。そのため、まずは品質の高い文章の作成に注力し、執筆後に細かいトンマナのチェックを実施するのがおすすめです。
掲載予定のメディアを確認する
テストライティングに限らず、Webライティングのときには掲載予定のメディアやサイトをしっかり確認するようにしましょう。
ユーザーは、そのメディアやサイトを一つのまとまりとして見ます。
サイト全体の記事が同じテイストで書かれている方が、統一感が出て、信用度が増す傾向にあるため、記事も既存のメディアに合う書き方が好まれます。
記事の書き方を統一するためには、まずトンマナを守ることが重要です。しかしそれだけでなく、その背景にある掲載予定のメディアを確認して、しっかりと掲載時のイメージを持っておくと、より質の高い執筆につながるでしょう。
簡潔かつ丁寧なコミュニケーションを心がける
チャットでのコミュニケーションのコツは、相手の文章のテイストに合わせることです。業界によっても、文章の丁寧さは異なってきます。基本的には相手の丁寧さに合わせた対応をしましょう。
例えばIT系のクライアントだと、発注などの窓口は人事が請け負っていて「かしこまりました」を使うけれど、原稿のコメント欄は開発者が対応して「OK!」みたいなケースがあります。それぞれの担当者の方に合わせて、挨拶文を入れたり、挨拶文は無しで要点を絞って伝えるなど、チャットの返信を調整しています。
指示内容を言い換えて確認する
指示内容がよくわからないけれど、「聞くと気分を害してしまいそうで怖い」または「聞くのが恥ずかしい」と思ったことはありませんか?
しかし、「わかったフリ」は絶対にやめましょう。
「理解力が低いと思われるのが不安…」という方におすすめの方法が、クライアントの要望は言い換えたり、まとめたりして、クライアントに伝えることです。例えば、複数のチャットに分かれて要望がきている際に、箇条書きで要点をまとめて伝えます。
これは不明点の有無に関わらず使え、お互いに理解が正しいかを確認できます。また、理解に誤りがある場合にも指摘しやすくなります。普段のコミュニケーションにもおすすめです。
一晩寝かせて確認し、余裕を持って納品する
執筆が完了したら、必ず文章を見直しましょう。その際のコツは、一晩寝かせて文章を読み返すことです。
人の頭は都合よくできていて、文章を読み慣れると誤字や脱字に気づきづらくなります。そのため、一晩寝かせてリフレッシュした頭で再度チェックすることが大切なのです。
また、余裕を持った納品も大切です。早ければ前日、最低でも納品日時の1時間前には納品するようにしましょう。万が一、不手際があった際にも対応しやすくなります。
ただし、早くできたからといって、早すぎる納品は基本的におすすめしません。ライターとしては納品日に余裕がある方が融通がきくからです。
文字数は気持ち多めにする
依頼文字数よりも下回らないようにしましょう。小論文などでは9割書け、と言われますが、Webライティングでは10割以上が求められます。
だからといって、5000字の想定文字数に対して、5001字で納品するのも印象が悪いためおすすめしません。クライアントに、「最低限の文字数にするために本当は書くほうが良い内容まで削っているのでは?」という疑念を持たれかねないからです。
もちろん多すぎる必要もありません。目安としては「100字程度〜依頼文字数の1割以下くらい多めの文字数」で執筆しておくと安心です。
テストライティング報酬の相場

テストライティングの報酬における一つの目安は、「正式依頼時の半額」です。
例えば、正式依頼の想定が文字単価2円✕3000文字=6000円であれば、テストライティングは文字単価1円✕3000文字=3000円です。正式依頼の記事単価10000円であれば、5000円です。
もちろん文字数や内容の難易度によっても異なってくるため、これはあくまでも目安です。
クライアントによっては希望額を聞いてくれるケースもあります。希望額を聞かれた場合の相場としても、「テストライティングは正式依頼の半額」と覚えておくとよいでしょう。
まれに「報酬なし」というテストライティングも存在しますが、これは悪質な案件である可能性が高いです。
悪質なテストライティングの特徴

テストライティング自体は悪いものではありませんが、クラウドソーシングサイトには初心者を狙った悪質なテストライティングが存在するのも事実です。
悪質なクライアントは、テストライティングを利用して格安で大量の記事を集めようとします。テストライティングでも著作権は譲渡するため、不合格にした記事も含めて、クライアントは納品された記事をすべて勝手に使えるのです。
悪質なテストライティングはWebライターの労働を搾取し、自信を喪失させます。何もいいことはありません。次のような場合は、テストライティングへの応募の取りやめを検討しましょう。
- 報酬が「半分以下」または「報酬なし」
- 文字数が多すぎる
- 複数の記事を書かされる
- SNS登録や教材購入など、テストと関係ない要望をする
報酬が「半分以下」または「報酬なし」
テストライティングはテストといえども、記事を納品してその権利を譲渡します。その労働と記事の対価として報酬が発生するのは、当然のことです。
「初心者だから……」や「不合格だから……」と報酬なしを受け入れる必要はありません!!
「報酬なし」のテストライティングへの応募は絶対に避けましょう。悪質な利用を目的としたケースが多くあります。
また、報酬が一応発生するものの、数百円といったクライアントも要注意です。無料じゃないから大丈夫かもしれない…という淡い期待を持つ初心者をカモにしている可能性が高いといえます。
「半額よりも多少低いけれど、作業量は減らしてあるし、キリのいい額だから」など、十分に納得できる理由があれば、もちろん半額以下でも大丈夫ですよ。
文字数が多すぎる
ライティングスキルを判断するために、10,000文字も書く必要はありません。
例えば、「採用されれば文字単価が1文字3円!!(テストライティングは10,000文字で500円)」という内容は、採用する気がなく、悪質である可能性が高いでしょう。
テストライティングの文字数は分野や内容にもよりますが、3000字〜多くても5000字程度と考えておくとよいでしょう。
複数の記事を書かされる
テストライティングで作成する記事は1本が基本です。1記事以上を要求してくる場合は、悪質なクライアントである可能性が高いので基本的に応募しないようにしましょう。
「記事10本あたりの納品スピードを知りたい」といった理由を挙げるケースもあるようですが、これも理由にはなりません。そのライターが1本書いてみて、判断すればよいのです。
よほど納得できるような理由がない限り(今まで納得できる理由など見たことありませんが)、複数記事を求めるテストライティングは避けましょう。
SNS登録や教材購入など、テストと関係ない要望をする
テストライティングにおいては、基本的に構成作成と執筆以外の作業は発生しません。SNS登録や教材の購入、モニターの体験などの要望が来た場合は応募を辞退しましょう。
特に、支払いが生じるようであれば、悪質なクライアントである可能性が極めて高いといえます。そのような場合は、応募を辞退し、クラウドソーシングサイトの運営に通報しましょう。
テストライティング以外で採用される方法はある?

テストライティングしか採用される方法はないのか…、というと、そんなことはありません。テストライティング以外の採用方法をご紹介します。
サンプル記事
いちばん手軽な方法が、案件への応募時にサンプル記事を提示することです。
案件募集では、実績の提示が求められるケースが多くありますが、初心者Webライターだと実績がなくて困るところです。そこで活用するのがサンプル記事です。
サンプル記事とは、Webライターが実力を示すために架空のテーマで作成する記事のサンプルです。サンプル記事のメリットは、納品しないため使い回せる点です。
例えばGoogleドキュメントでサンプル記事を作成し、閲覧権限のみで公開設定をします。そして、公開用のURLを案件応募の際にクライアントに提示するのです。
実際の案件実績よりは劣りますが、何もなしで応募するよりも受注につながりやすくなります。複数の分野の記事をストックしておき、案件内容に合わせて提示するのがおすすめです。
個人ブログ
ブログを開設して、そのブログ記事を実績として提示するのもおすすめの方法です。クラウドソーシングサイトのWebライターのプロフィール欄にブログのURLを載せている人は多く、それは営業ツールとしてブログが使えるからです。
もし、ブログのアクセス数を伸ばせれば、ブログの問い合わせから仕事の依頼がくることもあります。ただし、一般的にブログでアクセスを集めるためにはスムーズにいっても半年〜一年と、時間がかかります。すぐに案件受注や収入につながるわけではない点には注意が必要です。
ただ、ブログはWebライターのスキルアップに必要なライティングの練習やSEOの勉強になるため、Webライターの方には本当におすすめです。
ポートフォリオ
馴染みのない方も多いかもしれませんが、ポートフォリオを作るという方法もあります。ポートフォリオは実績を集めたもので、作品集みたいなものです。過去に受注した案件の内容をまとめて掲載することで、実績や仕事のバリエーション、内容などをクライアントに一覧で提示できます。
Webライターの場合は、クライアントの企業名や公開記事のURLをポートフォリオとしてまとめます。例えばクライアントとしては、プロフィールを見て良さげなWebライターを見つけた際には、その実績も確認したいものです。そこで役立つのがポートフォリオです。ポートフォリオサイトは案件応募の際にも活用できます。
作成した記事の公開URLや文章の内容をポートフォリオへ掲載する際は、クライアントの許可が必要です。
作成した記事は、納品とともに著作権もクライアントに譲渡します。そのため、クライアントの許可なく記事を掲載したり、執筆者として紹介したりしてはいけません。クライアントの許可は絶対にもらいましょう。
ポートフォリオの掲載許可がもらえるかどうかは、ケースによります。例えば、企業と直接やり取りしていたり、スカウトで仕事をもらったりした場合は、掲載許可を得やすいでしょう。一方で、企業との間にWebディレクターやSEO会社を挟んでいる場合は、許可を貰えない傾向にあります。
断られたところで損する話ではないので、ポートフォリオの掲載については、とにかく「納品の際にポートフォリオに掲載してよいかクライアントに聞く」ようにしましょう!
1件でもポートフォリオに掲載できるものがあれば、案件応募での強い武器になりますよ。
卒業後に仕事をもらえるWebライター講座に申し込む
Webライター向けの講座では、卒業後に仕事をしやすいように、最初の実績となる案件を紹介してくれるものもあります。講座受講の費用がかかりますが、仕事を早く軌道に乗せられるというメリットがあります。
また、「テストライティングで不合格になったものの、何が悪かったのかわからない」というケースは多いのではないでしょうか。ライティングスキルの向上には、書いた文章へのフィードバックが欠かせませんが、なかなか他者からフィードバックをもらえる機会は少ないものです。
Webライティングは、指導を受ければ向上しやすいスキルです。自分一人では難しい、確実に成果につなげたい、という方は、一度講座の受講などでプロの手を借りることも検討してみてください。
安定した仕事を得たいという方は、ハンドメイドチャンネルの「ブログライター体験」がおすすめです。このブログライター体験は有料ですが、初心者コースであれば税込み2.2万円で、指導を受けながら5記事の作成を体験できます。
最大の魅力は、体験後のテストと審査に合格すれば、ハンドメイドチャンネルで文字単価1.5〜2円で、記名記事の制作を請け負えることです。
一般社団法人がWebライター育成を目的として運営しているため、手厚い指導ながらも、お手頃価格でWebライティングのノウハウを学べます。一度、チェックしてみてください。
【スキルアップで収入アップ!】「ブログライター体験募集」
![]()
テストライティングに落ちても「学び」を得よう

テストライティングの解説と受かるコツを紹介してきました。クラウドソーシングサイトでのやり取りでは、落ちた原因がわからず、戸惑ったり落ち込んでしまったりするかもしれません。
しかし大事なのは、落ちた経験を学びに変えることです。
この記事を読んでいるあなたは、次に向けたアクションを取ろうとしています。
落ちたことと向き合い、こうして対策すれば、日々、状況は良くなっていくはずです。なんせこの世には数多の会社があり、案件の応募は無限にできます!
この記事が、明日のより良い執筆につながることを祈っています!